社内公募の動機として最も多いのは現状の職場で何らかの不満がある状態があると思います。
人間関係、事業の撤退のリスク、キャリアチェンジ、勤務地の希望などなど。
この動機というのは、そのまま放置していくと最悪退職につながるシリアスなものもあるでしょう。
こういった観点から、人的資本的にみた社内公募のメリットを考えてみたいと思います。
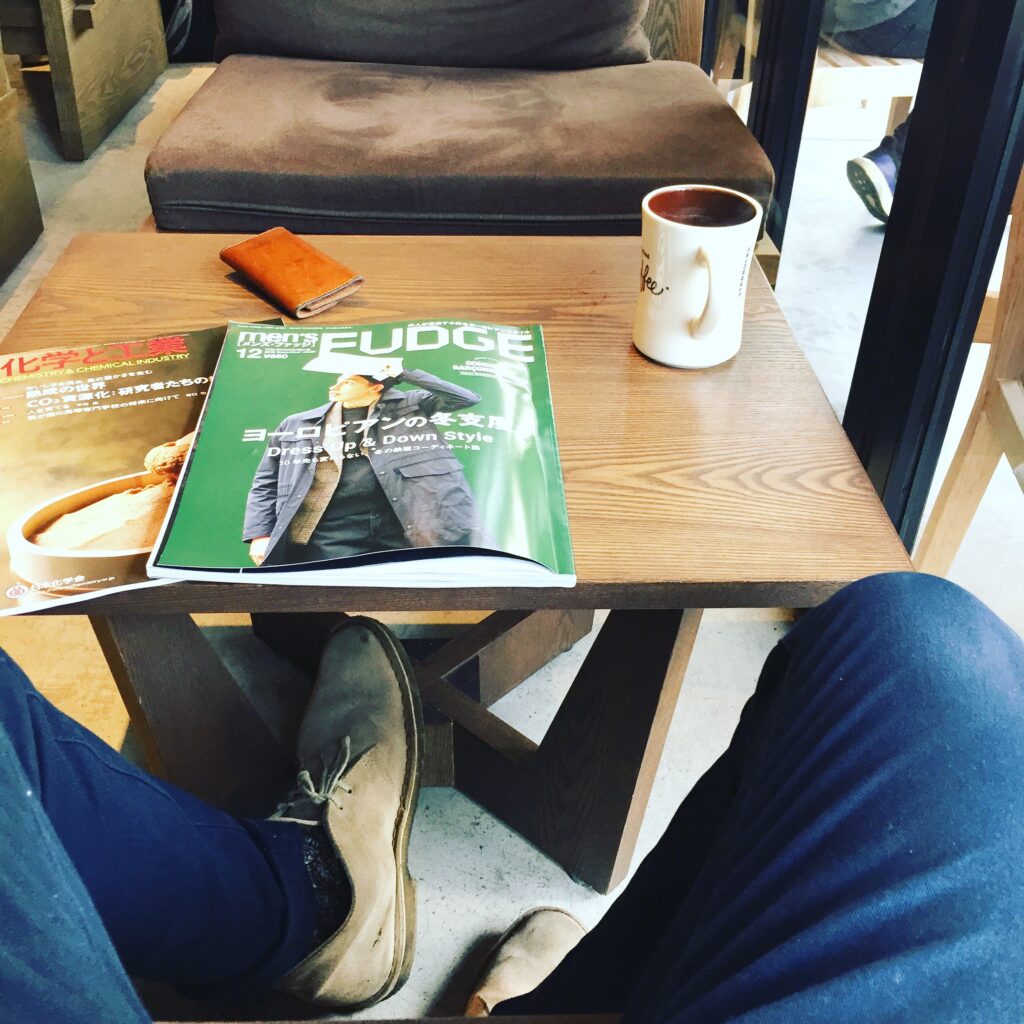
<プロフィール>
・30代メーカー技術系会社員
・高専本科、編入を経て東京の国立理系単科大学院を卒業
・新卒入社した会社で社内公募にて部署異動、職種を変更
・既婚(共働き)子供1人
・趣味はガーデニング
・米国株投資をメインに2020年から資産運用を継続
そもそも人的資本とは何か?
そもそも人的資本とは何でしょうか。
一般的には人間つまり「ヒト」の持つ能力を資本としてとらえた経済学の用語とあります。
具体的には、その人が稼ぐ生涯賃金といえます。
概ね、一般的な大卒サラリーマンは2〜3億円の生涯賃金があると言えます。
そのため、新入社員で入社して間もない方の人的資本は2〜3億円と言えますね。

一方で来月、定年退職を控えており、退職金もなく再雇用も予定していない方の人的資本は年金のみとなりますので数千万程度と考えられます。
このため、若い方ほど人的資本が大きく、歳をとるほど働ける期間、年金を受給できる期間が短くなりますので人的資本は小さくなっていきます。
人的資本から社内公募を考えてみる
人的資本からみて社内公募の最大のメリットは離職を防げるに尽きると思います。
例えば、上司のパワハラが強い場合を考えてみましょう。
パワハラが強いと自尊心が,傷つく。
何でこんなことできないんだ!
やる気あるのか
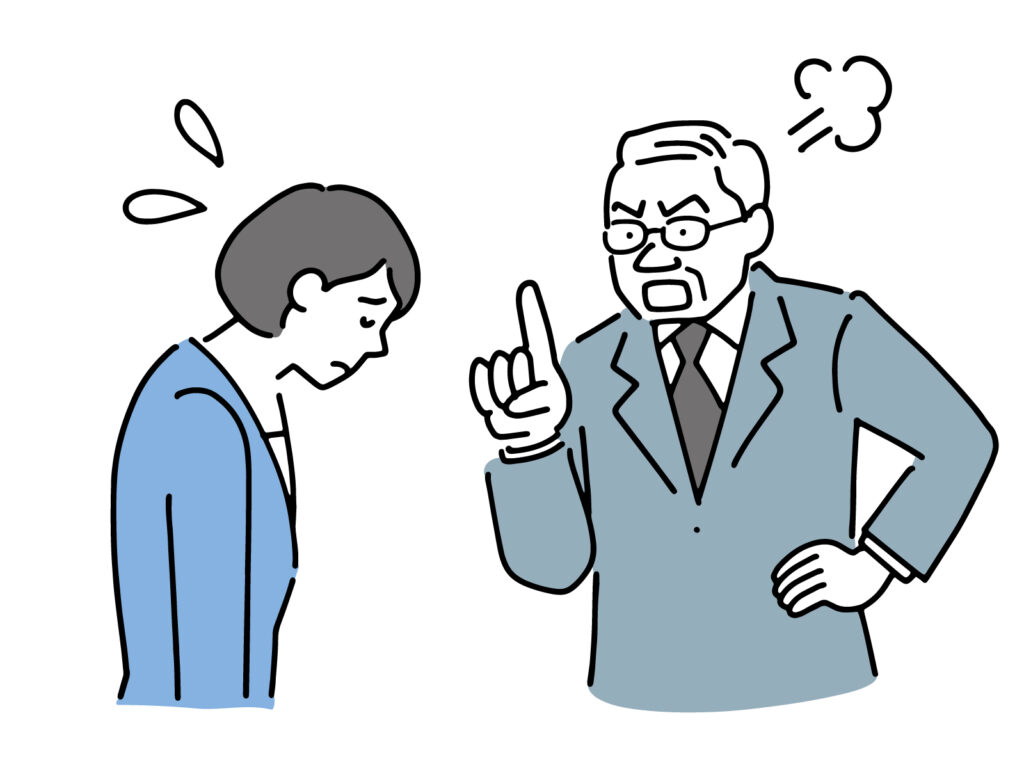
こんなことを言われると、誰だって自分の尊厳が低下すると思います。
こうなった場合、最終的にはメンタルを病み、離職につながることになります。
離職に繋がり、仕事ができなくなるとお金を稼げなくなる。
そうなると、人的資本、すなわち個人が生涯で稼げる金額、得られる金額が少なくなってしまいます。すなわち人的資本が毀損するということです。
この人的資本の毀損を防ぐために、社内公募はメリットがあると思います。
社内公募は職場を変えながら、会社は変わらない。
そのため有休はそのままです。
意外と、有休は持っていると便利ですよね。子供が熱を出した!子供の健診に行かなくては行けない!
だけではなく、自分が病気になった(子供が小さいと、病気をもらってきて親ももらいます)、旅行に行きたいなどなど。
不足の事態から、人生の充実まで有給があれば対応ができます。
また、社内的なシステム、メール、クラウド関係。全てがそのままで対応できる。
会社が変わらないことは、大きなメリットになるのではないでしょうか。
そして、社内公募で合格すれば、その上司とおさらば。
上司がストレッサーであれば、それを取り除きつつ、自分への変化を最も小さくすることができます。
人的資本という生涯という観点でみると社内公募のメリットが見えてくる。
人的資本とは、その人個人が生涯で得られる金額です。
この金額が減ることを、自分の環境をなるべく守りつつ防ぐことができる手段、これが社内公募と考えられます。
例えばパワハラ上司に当たってしまった場合、有給等はそのままに上司と違う職場に自分の意思で移動ができます。
この結果、メンタル疾患等を未然に防ぐことができれば、人的資本を守る上で非常に効果的です。
多くの人が、その瞬間の年収にとらわれている気がします。
30代の平均年収などもニュースサイト等で取り上げられることも多いですし、何より比較できるからですね。
人間も所詮は猿なので、序列や比較に縛られ追い求めがち。
だからこそこの競争を横目に自分の人的資本はどのくらいか。
これをどう守っていくかを考えてみるのもいいかもしれません。
私も、社内公募で同期の等級より低い等級で働いている期間もありました。
辛いですが、今考えると辛い職場から動いてよかったかなと思います。
多少のインカムが少なくなったとしても、しっかりと支出をコントロールして、投資をして資産を形成していればそこまで大きな問題にはならないと思うからです。
確かにお金は用途はたくさんあるので、貰えるだけもらった方がいいですけど、欲張って働けない状態に至るぐらいであれば守りの異動をしてみてもいいのではないかなと思います。
ぜひその瞬間の年収にとらわれるのではなく、自分の生涯稼ぐ金額に対してどう守っていけるかを考えてみるのも考えてみてはいかがでしょうか!

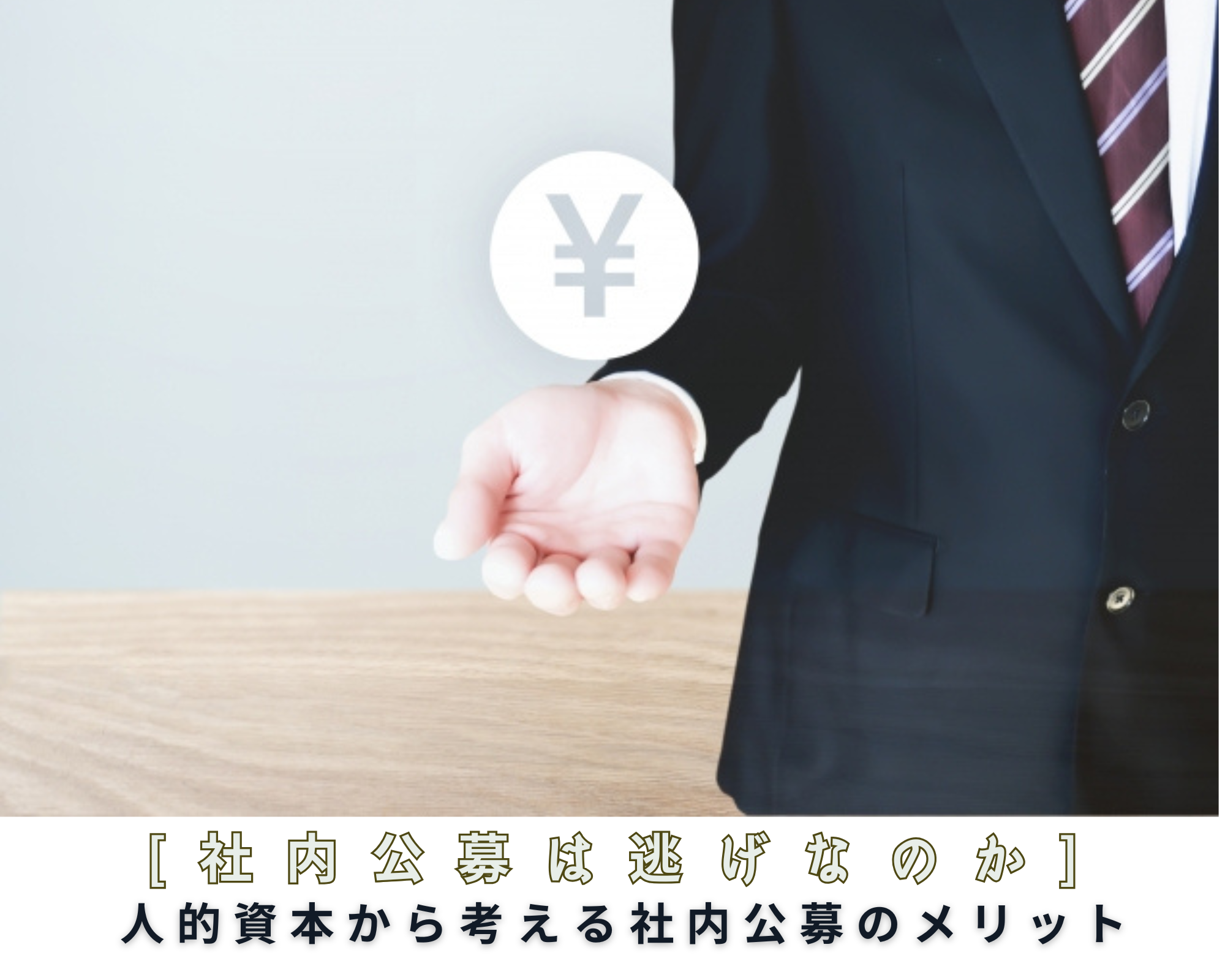
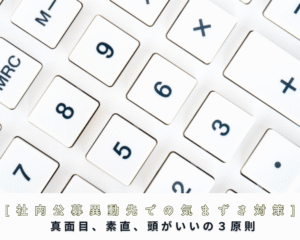


コメント